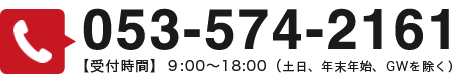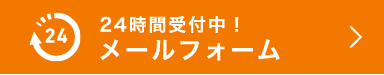2017年2月25日(土) 892/1000
<働く喜び>
皆さん、おはようございます。
「宇宙も神様もぜんぶ味方につける習慣」(宝島社) その21
著者:小林正観氏
******************************************************************************************
自分が汗を流すことで周りの人の役に立ち、喜びを与えることを「働く」と言います。
「はた(周り)」を「楽」にするので「はたらく」です。また、「仕事」は「(喜ばれる)事」に「お仕えする」と書きます。どちらも、お金を得るとか報酬を得るという概念の言葉ではありません。
人間の仕事の本質は、お金を稼ぐことではなく、自分がいかに喜ばれる存在になるか、ということです。それは「いかにたくさん頼まれごとが来る人になるか」ということに尽きます。そのように喜ばれる存在であり続ければ、商売的には栄えていくのです。
40年ほどいろいろな仕事や商売を見てきて、わかったことがあります。それは、うまくいっているところは「どうしたら喜ばれるか」を考えていて、うまくいかないところは「どうやって儲けるか」を考えているということ。どうやって儲けようかと考えている間は、お客さんは来ません。喜ばれることだけを考えていれば、数字は後からついてくるのです。
******************************************************************************************
最近とくに働くことが罪悪かのような風潮があり、労働時間の法規制がますます厳しくなっていくような政治的な動きがあります。決して働き過ぎを推奨するわけではありませんが、このような風潮が広がっていけば、仕事そのものの本質がねじ曲がっていくように思えてなりません。
仕事というのは、生活の糧を得るためであると同時に、人間としての成長する「場」であると考えるのです。仕事と真剣に向き合い、仕事を通じて自分を高めていこうという人が、年齢と重ねるにつれて人間の風格が備わっていくように思えるのです。
仕事を単に給料を稼ぐだけの道具とするならば、その人の成長はなく50歳になっても思考は子どものままということになる。なぜなら、楽(らく)なところから成長はあり得ないからです。
仕事は大変であり、辛く厳しいものであるから成長があるわけです。我慢や忍耐を覚え、働く喜びを体感し人間的な成長をする場所が仕事であると考えるのです。
もしそのことさえも意味のないこととなれば、仕事は単なる金儲けの道具と化し、世の中が暗黒となってしまいます。近年その流れの中に突入しているように思えたりします。
だから経営者は、会社を教育の場とし働く喜びを感じてもらえるような仕組みを創らなければ、企業としての存在価値を失うのではないかとさえ思えてしまいます。
自分の仕事がお客様の喜び、働く仲間への喜びにつながり、自分の存在価値を見つけることができれば、働きがいや生きがいになっていくのではないでしょうか。