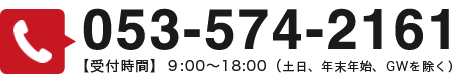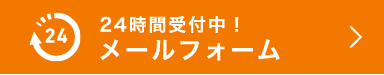2017年1月29日(日) 865/1000
<人を伸ばす力>
皆さん、おはようございます。
修養のすすめ(致知出版社)より引用 その13
著者:北尾吉孝氏
******************************************************************************************
人材教育の在り方として『論語』にある「君子は人の美を成す。人の悪を成さず。小人は是に反す(君子は人の長所を見つけて、一緒になってそれを伸ばすのを助けてやる。それによって悪いところは目立たなくさせてやる。小人はこれと正反対である)」という言葉があります。
教える人はそこまでして初めて教えを完結する、つまり教え育てることになるのだというふうに教育というものを捉えるべきですが、「悪いところ」そのものに対する処し方ということでは、いかに考えるべきでしょうか。
「短所があるなら短所を直そう!」という教育の仕方をする人が大勢かと思われますが、中には前述にた君子のようなやり方が寧ろ正しいと考える人もいて、どちらが良いのかは対象者の性質に拠るところも多くあるように思います。
私見を述べるならば、この長所を伸ばすことにより短所が消えてなくなるか、あるいは抑えられていくといった形で、短所に変化を及ぼすということは間違いないと思います。ですから、長所をできるだけ伸ばすという教育方法が基本的には正しいだろうと考えています。
例えば、親が子供に対してあるいは先生が生徒に対して、毎日のように「あれが悪い」「これが悪い」と朝から晩まで短所を責めたててみて、彼らの短所が直っていくという経験をした人は果たしてどれだけおられるでしょうか。結局短所にしても誰が直すかといえば、自分で、その短所に気づき自らを反省をし、そして自分自身が改めていく以外にないのであって、人間とは自らの意思で自らを鍛え創り上げていく「自修の人」なのです。それがもし正しいとするならば、自らが自らをより良く創り上げ築いていくべく、己を変えようとしない人に対して、その短所をどれだけ指摘し続けたとしても、そこに良い変化は起こらないでしょう。
他方、毎日のように「あれは凄く良かったね」、「これは素晴らしいね」と誰かを褒めるという場合、褒められた人は皆良い気持ちがするでしょうし、もっと努力していこうと思うはずです。だからこそ、君子は「人の美を成す」として長所を伸ばすのを助けてやり、一緒になってそれを磨いてやろうとするわけで、そうすることでその人自身がそれを磨いていくようになるのです。
******************************************************************************************
自分の短所というのは、気づいている部分とそうでない部分があるように思います。例えば、多くの人は、「自分は思いやりがある方か、ない方か」と問われれば、「思いやりはある方である」と答えると思うんです。なぜなら、本能的に自分を悪人にしたくないと意識が働くからじゃないかな。
でも周囲の人から見れば、「自分勝手で思いやりがない人だ!」とレッテルが張られているかもしれません。こういう人は、大きな失敗や挫折、または伝えてあげないと気づくことは難しいかもしれません。このような短所を隠すほどの長所というのは、なかなか難しいものです。
どんな人にも長所、短所があります。双方、同じ量が存在しているわけですが、人の短所は目につくものです。でも短所を直すなんてことは諦めて、寧ろ「短所は直らない」と考え、長所を伸ばすというやり方のほうが、その人をやる気にさせることになるように思えるんです。でも案外、褒めることをしていないようにも思えたりします。「褒めると叱る」、このバランスも大事でしょうね。
ちなみに滅多に褒められることのない社長という立場ですが、褒められると気持ちのよいものですね。やはり、「褒める」言葉は、人を伸ばす力があるようです。