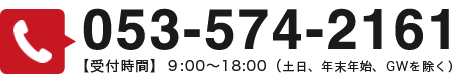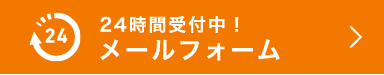2017年1月18日(水) 854/1000
<人間学を学ぶ>
皆さん、おはようございます。
修養のすすめ(致知出版社)より引用 その3
著者:北尾吉孝氏
******************************************************************************************
人間を形成する三要素とは、一つはご先祖様から脈々と受け継いできている「血」、次にどのような環境の中で育ってきたかという「育ち」、そして最後は「学問修養」のことです。
「血」や「育ち」を変えるのは非常に難しいことですが「学問修養」によって変えることが可能であり、そしてまた自分の品性を高めていくことができるようになるわけです。
ピーター・F・ドラッカーはその著書の中で「経営者がなさねばならぬことは、学ぶことができる。しかし経営者が学び得ないが、どうしても身につけなければならない資質が一つある。それは天才的な才能ではなく、実はその人の品性なのである」と言われているように、人間としての品性を高位に保つのは非常に難しいわけです。
必死になって学問修養しなければ、自らの品性を高位に持っていくことはできません。そして、これまであなたたちが小学校から大学まで習ってきた時務学と称する学問は、即ち言い方を変えれば末学のことを指しているのです。(※末学:重要でない枝葉末節の学問、未熟な学問)
ここから本格的に身につけていかなければならない学問は、本学なのです。人間としてこの世に生を受け、どのような人生を世のため人のために送っていくのかということを学ぶのが人間学であり本学なのです。今までの学問、即ち小学校から大学までの学問というのは、答えのある学問であり、歳と共に多少程度は上がっていくかもしれませんが、大体において知識を習得すれば答えが導き出されてくるものです。
しかしこれから、あなたたちが真剣勝負していかなければならない学問、あるいは修養というものはそう簡単に身につくものではありません。
「人生いかに生きるべきか」
「一体自分の天命とは何か」
「天はどのような能力や才能を自分に与えたもうたか」
「その能力や才能をどのようにして開発し、世のため人のために生きていくのか」
「自分と他の人間との関わり合いはどうなのか」
「自分と社会との関わり合いはどうなのか」
「日本だけでなく世界の中で自分はどうあるべきなのか」
といったことを日々考え続けていかなければなりません。
******************************************************************************************
”生きる”ということは、大変なことのようです。朝目が覚め、朝食を済ませ、会社で仕事をして、帰宅して夕食、そして就寝、週末は家族サービス。こんな幸せな日々の中に埋もれてしまい学ぶことを忘れてしまっている。そして時の経過とともに歳をとり何も学ばず、この世を卒業していく人が多いと聞きます。僕もその一人ですが。。。
北尾さんのおっしゃるとおり、本学という人間学を学び続け、自らの役割というものに気づき、実践していく過程の中で、品性というものが少しずつ身についていくのでしょう。
50歳を過ぎ、未だ品性というものがよく分からず、落ち着きもないものだから、まだまだ学び足らないようです。
「五十にして天命を知る」という論語の言葉がありますが、53歳になってしまったので、慌ててしまいます(笑)
「人生いかに生きるべきか」難しい問いではありますが、分からないというのではなく、考えて来なかったということでしょう。自分という人間を生かしていくためにも、人間学を学び、崇高なる問いの答えを見つけていきたいと思います。