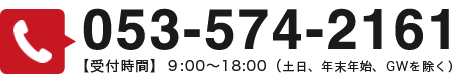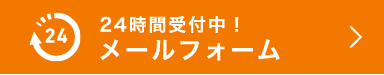2016年6月26日(日) 648/1000
<幸福度>
皆さんおはようございます。
「幸せの国ブータンに暮らして」より抜粋 その1
菅沼泰久氏
******************************************************************************************
1976年(昭和51年)は私が生まれた年でもあり、その頃の日本は高度経済成長の真っ只中にあったと聞きます。国家の経済成長こそが国民の幸せにつながるということを誰もが疑わなかった時代に、日本から遠く離れたヒマラヤの若い国王は、世界の先進国が向かう方向性に対して疑問を投げかけたのです。
現国王ジグメ・シンゲ・ワンチュクは、ブータンの第四代国王です。1972年に第三代国王がケニアのナイロビで急死し、若干16歳だった現国王がその跡を継ぐことになったのです。その当時国王は、村から村へと全国行脚をしていたそうです。村人たちの生活に触れた国王は、「我が国の民は、物質的には貧しいけれど、心は豊かである。この先近代化が進んで国民の豊かな心が脅かされるときがきたら、この国は滅びていくだろう」と語ったそうです。国王自らの「足」で行われた地道な国民把握活動の結果、GNH(国民総幸福量)という概念は生まれたのです。
GNHの概念においては、経済発展だけが国民の幸福度を測る指標とはならず、開発行為は物質的な豊かさと精神的な豊かさとのバランスを保ちながら行われるべきであるとされています。人間の精神的な満足度を保つために必要な自然環境保全や伝統文化の保存をないがしろにするような乱暴な経済成長を追求するべきでない、というのです。
また、人間の物欲が増大すればするほど幸福度は減少するという考えに基づき、自我の抑制が国民の幸福につながるという価値観も含んでいます。
「人間の欲望は、人間が得る情報量に比例して増大する」との考えから、ブータン政府はインターネットやテレビの導入にはとても慎重な態度を示したそうです。
******************************************************************************************
私の両親は戦前の生まれで戦後の食糧難を経験しています。それから70年が過ぎ、経済発展を遂げた我が国日本は豊かになった。しかし、ブータン国王は、経済発展と幸福度は比例するものではなく、反対に人間の欲望を増幅させ、人間の心を蝕み、国は衰退していくと考えているのである。
確かに、核家族化、ゆとり教育、受験戦争、個人主義、成果主義、利益優先などにより、人と人とを引き離し、人間関係が希薄になるような環境になってきているように思えてならない。
GNHと同じように会社は働く人の幸福度が増していかなれけば、組織が崩壊することを意味する。会社は仕事をする所であるから、働きがいを上げていかなければ幸福度は上がらないと考えるのです。 働きがいとは、働くことの幸せ、そして経済的幸せであると考え、社員の幸福度に貢献していくことが経営者の仕事でもあると思うのです。