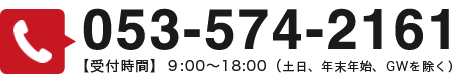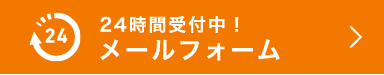2016年5月16日(月) 606/1000
<関を超える>
皆さんおはようございます。
致知6月号(致知出版社)より引用
特集「関を超える」 その2
******************************************************************************************
関。「かん」とも「せき」とも読む。「出入りを取り締まる門」と辞書にはある。
江戸時代、国境に関所を設け、人や物の往来を取り締まった。通行手形がなければ関所を超えて他国へ行くことは許されなかった。容易に通過できない関所を難関といった。
人生にも関所がある。
「人生にはしばしば出会わなければならぬ関所を幾つも通り抜ける旅路である」とは安岡正篤師の言葉である。関所を超えることで人は人生に新しい世界を開いていくのである。 禅家の修行では、厳しさが極点に達したところで、よく「関」の一語を浴びせかける、という。それを超えることで、禅者は無碍(むげ)自在の境地に達していく。在家も同じだろう。
関は人間を磨く通用門である。
******************************************************************************************
人はそれぞれの苦難がある。その人のレベル、つまりその人が耐えられるはずの苦難というものが必ずやってくるという。それも幾度となくあるというのです。
できれば苦難という辛いものは来てほしくないが、ここでは苦難を「関」と呼んでいる。
倫理法人会の万人幸福の栞では、「苦難は幸福の門」とあります。苦難は喜んで受けること、苦難は人間を大きく成長させると解説されています。「関」は人間を磨く通用門と言われることと同じことでしょう。
確かに辛いこと、苦しいことを乗り越えた時のことを振り返ると思い当たる節がある。過去には耐えられなかったことが、今、同じことが起きたとすると、その苦しみの深さは違うと感じる。これも経験であり、人間としての成長の証といえるのだろう。
では「苦難はなぜやってくるのだろうか」 と考えると、そもそも、人間は人生という道を歩んでいる。その歩みの中で人間として、また魂レベルの成長をするという目的を果たすことではなかろうか。仏教用語で言えば、輪廻転生のたびにレベルアップするためのステージが準備され、「関」という苦難がなければ成長がないからである。だから、苦難は喜んで受け入れるという理屈になると考えるのです。
この先にどんな苦難がくるのだろうかと考えると恐ろしくなる。できれば避けていきたいが、自分では選択できないようである。万が一、やってきた時、無理やりにでも
「喜んで受け入れる」ということを思い出してみよう。命までは取られることはないと思えば気も楽になる。
「関」は人間を磨く通用門ではあるが、その門をともに通る仲間がいれば勇気が湧いてくる。決して、孤独ではない。 「関」を超えれば、違う景色が見えてくる。違う次元の意識を体感できるのではないだろうか。やはり「関」を超えるには、やはり強い勇気が必要なのでしょう。
話は変わるが、過日、致知出版社主催による社内木鶏全国大会に社員20名と参加してきた。1600名の来場者にその空気感は熱気というより澄んだ朝の清々しさと言いたい。
全国から地区代表5社の社内木鶏会の取り組みの発表があった。社員代表のプレゼン、社長の念い、そして社員全員のエール。実に感動した。社員さんのイキイキとした姿、団結力は見ている我々が胸を熱くした。
感動大賞を受賞した九州地区代表(鹿児島県)の株式会社てまひま堂の吉岡社長の語った言葉が印象に残った。
これからの時代は「本物の時代です。本物は社内木鶏会を実施している会社です」
この言葉には勇気をもらった。致知の本を読み、感想文を書き、発表する社内木鶏会は、人間力を高め、よい人間関係をつくるためのも。
当社の社内木鶏会はスタートして10ケ月。まだまだ理解度が低いが、私にとって「関」ともいえる。これを乗り越えて2020年全国大会の舞台に正々堂々と立つと誓う。