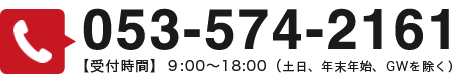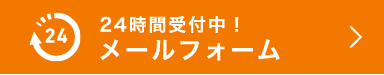2016年4月10日(日) 571/1000
<あの世への準備期間>
皆さんおはようございます。
致知出版社 致知4月号より
禅語に学ぶ「水流れて元海に入る」より抜粋
鎌倉円覚寺管長 横田南領氏
******************************************************************************************
人は生きている間に、一所懸命になって何かを集めている。財産を集めようとしたり、或いは家族の幸せを求めようとしたり、それぞれ何かを得ようと努力している。
そんな努力をしている人を、実に無情にも死は連れ去っていってしまう。東日本大震災の例を持ち出すまでもなく、死は突然と襲ってくる。いつであるとも予測することは困難である。
生とは何か、死とは何か、人間にとって最も根源的な問いである。死は全てを奪ってしまう。財産であろうと、地位であろうと、家族もみな失うことになる。「死は喪失にほかならない」と言われる。また西洋医学においては、生こそ価値のあることであり、あらゆる手立てを尽くして生を求めている。その意味に於いては「死は敗北」であるともいえよう。
しかしながら、単に死が喪失であるならば、私たちの生涯は、失うためにつみ集めるという実に空しい行為になってしまう。死は敗北であるならば、やがて訪れる敗北の為に日々努力していることになってしまう。それではあまりにも寂しいことではないか。
「人は天地の本源から生まれて暫(しばら)くこの仮のこの世に身を寄せるに過ぎないが、死はこの仮の世を去ってもとの本源に帰ることである」と解説されている。
この世に仮の客としてやってきた。死を迎えるということはもとに故郷に帰ることである。死生観を明らかにすることは、死を見つめて積極的に生の意味を見出すことにほかならない。
人は死に直面してはじめて、いのちとは何かを真剣に考える。死は喪失であり、敗北ならば、恐ろしいばかりであるが、大いなるいのちと一つになる、永遠なるものとつながっていると気づけば、死の恐怖からも解放される。
死は喪失でも敗北でもありはしない。大いなる仏心に帰るのである。帰るのであるから不安になることも恐れることもない。
亡くなった人の姿を見ることも、声を聞くこともできないが、大いなるいのちと一つになって生き続けている。どこに生きているか。それは、この今であり、ここを離れはしない。
******************************************************************************************
お金を一所懸命に貯めることに必死になることは大切であり、同時にお金もとても大切である。しかし、お金が全てであると思い人を押しのけ、「あいつは金の亡者だ!」と言われ、孤独となっていく人がいる。でもせっかく貯めたお金は、死と同時に全て自分の手元から離れていってしまう。
「お金を貯めることはよいことであるが、お金の使い方を誤ってしまった。お金だけを信じてきたが、多くの人を犠牲にし周囲の人を不幸にしてきたことか。」とあの世で自分の生き方を振り返り反省をすることになるのではないだろうか。
生きること、死ぬこと。この世とあの世の存在。それぞれ意味があるのでしょう。この世の人生は長いようで短い。いつか死ぬ。死ぬことは怖いが、死ぬまでになにをするのか。もし何もできなかったとするならば、後悔が残りまだ死にたくないと嘆くことになってしまう。
毎日、朝飯を食べ会社に行き、帰って寝るという日々同じことの繰り返しではあるが、残された人生を自分のためだけではなく、何か人の役に立つこと、それを実践することが、生きがいになるのではと考えるのです。大それたことをしなくてもいい。ほんの少しでもいい、それを継続していくことが大事じゃないだろうか。そして、その先にあるものが充実した人生という思いに至り、最後の日を迎える時に「悔いなし!」と言い切れるのではないだろうか。
毎日、死に向かって時間を使っている。だからこそ、時間を大切に無駄にできない。
この世はあの世へいくための準備期間だと考えてはどうだろうか。