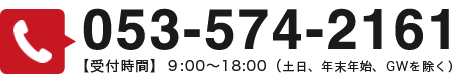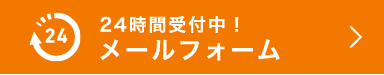2016年2月26日(金) 527/1000
<生きることを考える>
皆さんおはようございます。
致知出版社 致知3月号
「感動の歴史が子供たちの道徳を育む」
横浜市公立中学校教諭 服部 剛氏
******************************************************************************************
よく「価値観を押しつけるな」と言う人がいますが、まず価値観を与えないことには、人間は弱いので必ず迷走してしまいます。その挙げ句が、この個人主義の世の中ではありませんか?
戦後教育では「命を大切にしよう」ということが至上命題のように教えられてきましたよね。命はもちろん大切ですが、偏向した人権教育がそれに拍車を掛け、世の中がエゴイズムに流れていったのも事実だと思うのです。
私はむしろ、この百年足らずの短い人生で何を成し遂げるかという、いわば命の使い方、志を教えることこそが大切だと思います。
その上で、世の中には自分の命を懸けてでも守るべきものがあるという価値観があることを教えていく。この価値観が分からないと、誰かのために命を擲(なげう)った先人の偉大さを理解することができず、単に「かわいそう」で終わってしまいます。
******************************************************************************************
「子は親の鏡」といわれるように、子供は親の影響力は大きいので親の責任は重いものです。なぜなら世の中に立派な人間を送り込む義務があるからです。
父親として子育てに何をしてきたかと言えば反省しきりです。女房に任せっきりだった父親のように思います。
親は子供に生きる上での考え方を伝えることはとても大切なことです。なぜなら一番身近にいる親が正しい考え方を教えなければ誤った考え方を身につけてしまいます。
私たちは戦後教育の中で点数を取る教育を受けてきた。
いい点数を取り、いい高校に行き、いい大学に行き、いい就職先につくことが人生の勝者であるかのような教えを受けてきたように思います。いわゆる受験戦争と言われた時代です。
勝者がよく、敗者が悪く、失敗すれば落後者となるとなれば、人を押しのけ、人を踏み台とし、ますます心が荒んでいってしまう。これではよい世の中になるとはいえません。
そんな教育を受けた私たちは、今一度、生きる上で大事な考え方を勉強しなければ、子供たちに正しく教えることはできないのではないだろうか。
年齢に関係なく働く仲間と共に学び、伝え、価値観の共有をしてこそ、「生きることを考える」という命題への挑戦に向かうことができるのではないだろうか。
まずは家庭から、そして会社にその風土をつくっていきたいと考えています。