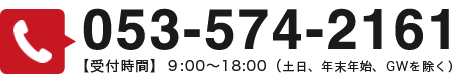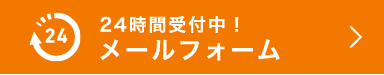2016年1月22日(金) 492/1000
<死の恐怖からの開放>
皆さんおはようございます。
致知2016年2月号
「がんの神様ありがとう」より引用
育生会横浜病院院長 長堀 優氏
筑波大学名誉教授 村上和雄氏 対談
******************************************************************************************
(長堀)
西洋的な二元性に立つと、「生」に対して「死」は敗北だと考えられてきました。
(村上)
しかし死が敗北だとすると、人生の最後はみな敗北で終わってしまう。そんなおかしな
ことがあるんですか。
(長堀)
東洋には「生死一如(しょうじいちにょ)という言葉があって、これはよく生きるためには
死を意識しなければいけないという発想から生まれています。
ところが現代社会では、その死を遠ざけてしまった。だから多くの人たちが生きる意味
を見失ってしまったんです。
これだけ生活が豊かになったのに、毎年自殺する人が約三万人もいて、子供たちの心が荒れている原因も、そこにあると私は見ています。
******************************************************************************************
「生」に対して「死」を敗北と考えることの不自然さは妙に納得できる。「死」を敗北や、「死んだら終わり」と考えてしまうと、この世の意味を失ってしまう。
人間は、毎日少しずつ死に向かって進んでいる。だからこそ、自分の存在意義、残されたこの世の時間を如何に過ごすか、という生き方を考えるようになる。死生観と言ってもいい。つまり死ぬことと、どのように向き合うかが、「今を生きる」ことに繋がってくる。
松下幸之助翁は、「死を恐れるよりも、死の準備のないことを恐れた方がいい」とおっしゃている。奥深い言葉である。
「人は死ぬ」ということを分かった時、この命を何に使うかを考え、日々精一杯生きることになると思う。その時、死の恐怖から開放されるのではないだろうか。