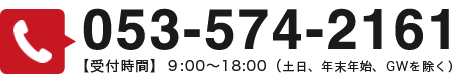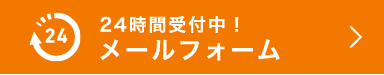2015年11月10日(火) 419/1000
<得と徳>
皆さんおはようございます。
致知11月号
「後から来る者たちへのメッセージ」 その4
日本を美しくする会相談役 鍵山秀三郎氏
********************************************************************************************
私は今朝も五時十五分から八時まで、三時間近く近所の公園の掃除と草取りをしてまいりました。誰に頼まれたわけでもなく、自分の意志でやっていることです。いまの時期は暑さに加えて、蚊に食われて大変です。別にそれをしたからといって、私には何の得にもなりません。それでもなぜやるのかと申しますと、人間は自分の得にならないことをやらなければ成長できないからです。
残念ながらいまの時代は、自分の徳になることなら一所懸命にやるけれども、自分の得にならないことはしないという人が多いですね。それではダメなんです。もちろん自分の得になることも大事ですけれども、それ以外に自分に何ら得にならないことも励んでいただきたいのです。
宮城谷昌光さんの「晏子(あんし)」という小説に、中国春秋時代の政治家、晏子が、
「益はなくても意味はある」
という場面があります。無益なことは必ずしも無意味ではなく、意味があるというのです。晏子という人は、無益なことにも意味を見出して行動する。そういう生き方を生涯貫きたいんですね。
********************************************************************************************
何かをするということには目的がある。「する」ということは、自分の利益になる、得になる。ためになるからするということと考えてきました。相手のために何かをして差し上げるということは、相手に喜んでもらいたいから、笑顔をみたいからという、究極に言えば、自分が喜びたいからという考え方もあります。
鍵山さんは違うという。自分の得にならなことをやらなければ成長できないというのです。素直な自分と向き合う、「こんなことをして何になるんだ!」という自分と向き合い、継続することでその本当の実践の意味に気づくのでしょうか。
「益がなくても意味はある」
益とは自分の「得」ではなく、「徳」というものではないだろうか。
「得」は自分の利益になること。利益を追えば追うほど遠ざかり、お金の臭気を放ち、
自分の周りからも人も金も離れていく。
「徳」は奉仕の精神とでもいいましょうか。人のため、世のためにやればやるほど徳が溜まっていき運もよくなっていくようなものではないだろうか。
徳を高めていくためには、靴を揃える、整理整頓する、掃除をする、元気な挨拶をする、いつも笑顔でいる、優しい言葉を使う、人に親切にする、約束を守る、相手を尊重する、正直に生きる。など何かを役に立つことをする。そんな風に思えています。これは意識してやろうとすれば誰にでもできること。しかし、口で言う
ほど簡単なものではないように思えてもいます。
自分を高める努力をすることは、小さな実践であると思うのです。