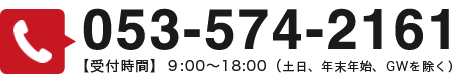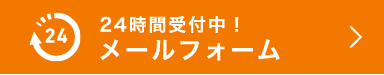2015年10月27日(火) 405/1000
<伝えること>
皆さんおはようございます。
致知11月より引用
特集 「遠慮―遠きを慮(おもんばか)る」より抜粋 その1
*********************************************************************************************
学識の人、小泉信三(慶応義塾大学塾長)にこんな話がある。
「日本の国土は自然によって与えられたものではない。長い年月の間に我々の祖先が手を加え造りあげ、我々に伝えてきたものである。
土地の開墾、耕作、道路、橋、ダム、港湾・・・・・・有形のものばかりではない。宗教、道徳、制度、風俗、学問、芸術、その総(すべ)てを含む日本の文化。これこそ我々が祖先から受け継いで子孫に伝える最も大切なものである。」
*********************************************************************************************
実家は浜松の田舎で小さい頃、夏の夜はホタル、カエルの大合唱。寝る時は蚊帳(かや)、近くの川はとてもきれいで夏はよく川遊びをして、おじさんがウナギをとっていた。家には土間があって年末は餅をついた。なんとも優雅な風景である。
お月見、お盆、祭り、七夕、いろいろな習わしがあったことを思い出す。その根本は全てのものに神様が宿っているという思想であり、日本は元来、八百万の神である。
今はどうだろうか。簡素化が進んで文化が廃れつつある。
省いてよいものと、そうでないものの区別がついていない。なんとも浅はかである。
文化の継承は、日本人としての心の継承と言える。しかし、その意義を感じられないでいるように思う。廃れているのは文化だけではなく、我々の感性とも言える。
福島原発の立ち入り禁止区域の映像がテレビで放映されるが、雑草が生え、家は荒れ放題。人間が手を入れなければ、あっと言う間に朽ち果てていく。
生きるということは、単に生きながらえるということではなく、大事なものを伝えるということでもある。自然も風習も一つひとつ先祖が守り育て、一つひとつ意味がある。
だからこそ、私たちは「伝えること」の大事さを振り返りたいと考えるのです。
それは、今ある自分は両親から命を受け継ぎ、その両親にそれぞれ両親がいたということを考えると、感じることができるのではないだろうか。
伝えることは、命に感謝することから始まると考えるのです。