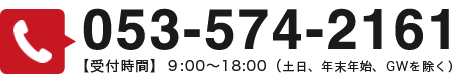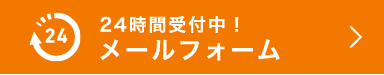2015年9月29日(火) 377/1000
<徳を生む>
皆さんおはようございます。
致知出版社
「現代に生きる二宮翁夜話」より引用 その4
中桐万里子氏著
*********************************************************************************************
ある学生さんから聞いた話を思い出しました。その方が飲食店で研修を受けていたとき、来る日も、来る日も皿を洗うことばかりさせられたと言います。だから思います。「これじゃぁ、なんの経験にもならないし、せっかく大学で勉強したことも、自分の力も、ぜんぜん活かせないじゃないか・・・・・」と。しかしある時、肚を決めます。「こうなったら洗い場の仕事を徹底してやるぞ!」と。
皿洗いとまっすぐに向き合っていると、目にとまるようになります。そこに残されていた料理です。お客様は何を残すのか・・・注意深く観察し続けます。すると、漬け物代わりのちりめんじゃこがよく残されていることに気づきます。ただし、たいていは手をつけてある。「味じゃなく、量の問題かな?」と感じます。
これを作り手に伝え、改善がなされ、ちりめんじゃこが残されることは減ったそうです。
洗い場の自分にしか果たせない役割をみつけ、働くことの楽しさがぐっと増したと語られていました。
ひなびて見えるそんな小さく「卑近」の場所こそ、大きな実益や実徳を生む力をもつ「富の源」「宝のありか」だ・・・・・。金次郎のように捉えると、新しい景色が見えてくるかもしれません。
*********************************************************************************************
チームで仕事をする場合、Aさんは、到底一人ではやりきれそうもない仕事を休憩時間もろくにとらずに必死にこなしている。Bさん、Cさんはそこそこ余裕があり休憩もとれている。そこでBさんは、余裕がある時間を使ってAさんの仕事を手伝った。Cさんは知らんぷりである。
成果はAさんが休憩時間がとれるようになったこと。Bさんの休憩時間が減ったことである。果たしてそれだけだろうか。
AさんはBさんへの感謝の気持ち、Bさんは感謝されたという喜び。
AさんとBさんのチームワーク力の向上、Bさんの工夫する力の向上、それだけではありません。AさんとBさんが力を合わせることにより、成果は2倍ではなく、それ以上になったということ。
何の得にもならないと知らんぷりしているCさんの行く末は知れたものである。
目の前の仕事に真剣に向き合い行動することは、自分だけではなく、周りの人にも幸せをもたらすことになる。そこには、成果という利益だけでなく、感謝、信頼という言葉に相応しい、相互の「徳」が生み出される。なんとも素晴らしいものだろうか。
身の周りの日常生活の中にこそ、徳を生み出す宝が眠っているように思えるのです。それの全て源は自身の実践以外にないということです。