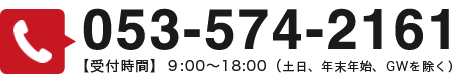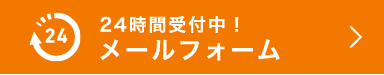2015年9月22日(火) 370/1000
<型にはめる>
皆さんおはようございます。
致知10月号より引用
「古典には集積された人間の知恵がある」より抜粋
安松幼稚園理事長 安井俊明氏
***************************************
教育の真髄は「子供に教え込む」のではなく、「子供からいろいろな資質を引き出す」ことにあると考えています。また、次代を担う子供たちに日本の文化を伝えることが、教育者の大きな責務の一つであるとも考えているんです。文化とは日本人としての基本的な型のこと。
例えば、朝起きたら「おはようございます」と挨拶をする。病気の人には「お大事に」と言う。これも挨拶や会話の型ですよね。
人の話を聞く時は背筋を伸ばし、凛とした姿勢で相手の目を見て静かに聞く。電車はバスでお年寄りが来たら席を譲るとか。
そういう型を身につけ、幼児を人としての軌道に乗せていくことが教育の第一歩だと思っています。その意味で、教育とは強制から始まるのです。
強制といっても無理やりやらせるのではなく、徹底して先生や年長の子の真似をさせるん
です。子供は真似る天才ですからね。
ところが、いまの日本の社会全体を見てみると、「自由、平等、個性」、この三つの言葉が
流行り文句です。逆に、「強制」とか「型にはめる」というのは悪い言葉なんですね、
一般の風潮として。
これはとんでもない話で、書道にしても、音楽にしても、型を否定したのでは教育は成り立たないわけですよ。
日常の挨拶にしても一つの型ですからね。
*************************************************************************************************
書道、茶道、剣道、柔道な「道」とつくものは型から入る。
茶道と見ていると、私にはさっぱりであるが、極めて「静」の奥深さを感じる作法ように思う。
今の幼児教育は、小学校に入学する前に算数や英語の英才教育へのスタートである。一番大事な幼児の時期に人間としての学びがない。その教育を受けてきた子供が大人になって、信じられないような事件が起きているように思うのです。
正座をして挨拶や聞く姿勢、食事や礼の作法などは、日本人としての基本の姿勢を躾けること。
「型にはめる」。
すなわち幼児の時にしっかりと基礎を身に付けた後に、個人としての個性を活かしていくことが大切
であると思うのです。
子供に自由にさせ、自由奔放に好きなことを好きなだけやらせる。子供の自由と意思を最大限にした
教育です。一見すると、子供の意思を尊重した素晴らしい内容のように思えます。
自由にさせることで、のびのびとした子供は育つだろうと思ってしまいますが本当にそうでしょうか。もしかすると、のびのびとは我儘になってしまうかもしれません。
自由とは好き放題にやらせることではないと思うのです。
高校生にもなれば、それはよいと思いますが、幼児時期ではキッチリと型にはめた教育が必要であると思うのです。